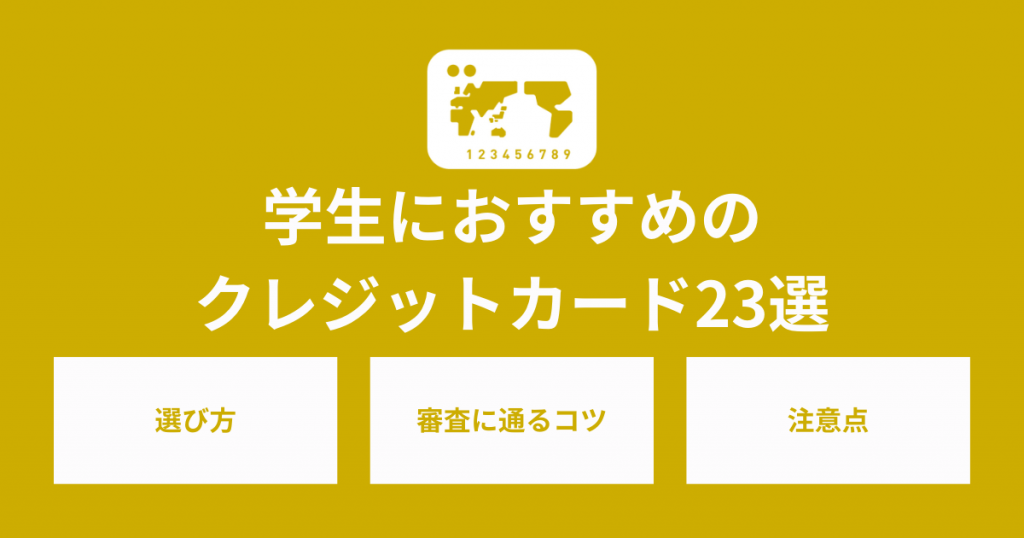ステーブルコインとは、法定通貨や資産と価値を連動(ペッグ)させることで価格の安定性を持つ暗号資産です。
ビットコインやイーサリアムのように大きな価格変動を伴う資金決済法上の「財産的価値」(資産)に比べ、決済・送金・投資の基盤として注目されています。
米ドルに連動するUSDTやUSDC、国内のJPYCなどが代表的で、2025年には金融庁による法整備も進展しました。
本記事では、仕組みや種類、主要銘柄、投資方法からリスクまで、初心者でも理解できるように徹底解説します。
2025年最新のステーブルコイン動向
2025年はステーブルコイン市場にとって大きな転換期を迎えています。
日本では金融庁がJPYCを円建てステーブルコインとして承認し、決済手段としての実用化が進展しました。米国では州政府が独自のステーブルコインを発行するなど、公的機関主導の動きも見られます。
さらに、CoincheckやSBI VCトレードといった国内取引所が新サービスを開始し、投資家の利用環境は整いつつあります。加えて、米国やEU、アジア各国では規制の明確化が進み、市場の信頼性と透明性が向上。
これらの動きは、ステーブルコインが投資だけでなく、決済・送金インフラとして定着することを後押ししています。
金融庁が円建てステーブルコイン「JPYC」を承認へ
日本では金融庁が2025年、JPYCを円建てステーブルコインとして正式に承認しました。
従来は暗号資産としての法的位置付けが曖昧でしたが、資金決済法に基づく認可により、JPYCは電子決済手段として利用可能になりました。
これにより、国内の加盟店での決済やオンラインサービスでの利用が広がる土台が整い、キャッシュレス化の加速につながる可能性が高いと考えられます。
特に、円建てで直接利用できる利便性は日本人ユーザーにとって大きなメリットです。
今後は、銀行や大手企業との連携が進めば、事業者側の決済手数料の低下によるポイント還元の拡大や、給料の週払いなど柔軟な給与支払いが実現しやすくなると期待されます。
米国・州政府発行のステーブルコイン登場
米国では一部の州政府が独自にステーブルコインを発行し、注目を集めています。
従来は民間企業による発行が中心でしたが、州政府が裏付け資産を担保することで信頼性が大幅に向上しました。
これは中央銀行デジタル通貨(CBDC)とは異なり、より柔軟かつ限定的な運用が可能です。具体例として、FRNTと呼ばれる州政府発行コインがあり、州内の公共料金支払いや地域金融システムに導入されています。
こうした動きは、ドルの国際的な優位性を維持する狙いもあり、今後は連邦レベルの規制やCBDCとの連携も視野に入ると考えられます。
国内取引所(Coincheck・SBI VCトレードなど)の新サービス
国内でも取引所がステーブルコインの取扱いを拡大しています。CoincheckではDAIやJPYCが購入可能となり、日本円から直接買える利便性が投資家から評価されています。
SBI VCトレードは、米ドル連動型のUSDCを導入し、金融機関ならではの信頼性とセキュリティを提供。
bitbankも対応銘柄を増やし、ユーザーの選択肢が広がりました。
これにより、従来は海外取引所を利用せざるを得なかった日本の投資家も、国内の法規制下で安心して取引できる環境が整いつつあります。
今後は他の国内取引所も追随する可能性が高いでしょう。
世界市場の成長と規制動向(米国・EU・アジア)
世界市場では、ステーブルコインの取引量と利用シーンが拡大し続けています。
米国では規制法案が成立し、発行体の準備金や透明性に厳格な基準が設けられました。
EUでもMiCA(暗号資産市場規制)が導入され、投資家保護と市場の安定性が強化されています。
アジアではシンガポールや香港が積極的に法整備を進め、地域の金融ハブとしてステーブルコインを受け入れる姿勢を明確にしました。
これらの動きにより、ステーブルコインは単なる投資対象にとどまらず、国際送金やデジタル決済のインフラとして国際的に定着しつつあります。
ステーブルコインとは?基本の仕組みと特徴
ステーブルコインとは、法定通貨や資産に価値を連動させて価格を安定させた暗号資産です。
従来の暗号資産は値動きが激しく、投資対象としては魅力的でも日常の決済や送金には不向きでした。そこで登場したのがステーブルコインです。
特徴を整理すると以下のとおりです。
- 価格の安定性:法定通貨や資産に連動(ペッグ)
- 利用のしやすさ:暗号資産の利便性を保持
- 用途の広がり:決済・送金・資産保全・DeFiで活用
特に、米ドル連動型(USDC・USDT)や日本円連動型(JPYC)は利用シーンが増え、暗号資産市場の基盤的存在となりつつあります。
ステーブルコインの定義と「安定性」の意味
ステーブルコインは、「安定した価値を持つ暗号資産」として定義されます。
最大の特徴は、担保資産を裏付けに価格を一定に保てる点です。
例:主要ステーブルコインの安定性
| 銘柄 | 連動対象 | 価格維持の仕組み | 特徴 |
| USDC | 米ドル | 発行体がドルを準備金として保有 | 高い透明性・監査あり |
| USDT | 米ドル | 発行体がドル資産で担保 | 世界最大の流通量 |
| JPYC | 日本円 | 日本円建ての資産に裏付け | 金融庁承認・国内利用可 |
この安定性により、投資家は相場急落時の避難先として利用でき、企業はボラティリティの少ない決済手段として導入可能です。
法定通貨や資産との価格連動(ペッグ)の仕組み
ステーブルコインは「ペッグ」によって安定性を実現しています。
ペッグとは、ステーブルコイン1単位=法定通貨や資産1単位と価値を連動させる仕組みです。
- 法定通貨ペッグ:USDC(1USDC=1USD)、JPYC(1JPYC=1JPY)
- 資産ペッグ:XAUT(金に連動)、コモディティ型
発行体はペッグを維持するために、発行枚数と同額の資産を準備金として確保します。またブロックチェーン技術を活用することで、透明性(準備金状況の公開)と即時性が担保されます。
ビットコインなど他の暗号資産との違い
ビットコインやイーサリアムは供給量や需給により価格が変動するため、投資対象としては魅力的でも安定した決済手段には不向きです。
違いを表で整理すると:
| 項目 | ステーブルコイン | ビットコイン等(変動型暗号資産) |
| 価格変動 | 安定(法定通貨や資産に連動) | 大きい(需給で変動) |
| 主な用途 | 決済・送金・資産保全・DeFi | 投資・投機 |
| 安全性・利便性 | 担保資産に裏付け | 価格乱高下による不安定性 |
| 投資家の使い方 | リスク回避・決済手段 | 値上がり益を狙う投資対象 |
つまり、ビットコインは「投機性」、ステーブルコインは「安定性」を重視した資産として位置づけられます。
ステーブルコインの種類と仕組み
ステーブルコインは、その裏付け資産や設計方法によって大きく4種類に分類されます。
代表的なのは、米ドルなどの通貨を担保にする「法定通貨担保型」、イーサリアムなどの暗号資産を担保にする「仮想通貨担保型」、金などの商品に連動する「商品担保型」、そしてアルゴリズムで需給を調整する「無担保型(アルゴリズム型)」です。
それぞれメリットとリスクが異なるため、利用目的に応じて選択することが重要です。
法定通貨担保型(USDC・USDTなど)
ステーブルコインの中で最も普及しているのが法定通貨担保型です。
これは、発行枚数と同じ金額の米ドルや日本円を準備金として保有することで価格の安定を保証します。
代表例は「USDC」と「USDT」で、どちらも1枚=1ドルの価値を維持しています。特にUSDTは世界最大の流通量を誇り、暗号資産取引やDeFiで広く利用されています。
一方、USDCは定期的な監査報告を公開するなど透明性の高さが評価されています。つまり、法定通貨担保型は安定性が高く、初心者でも扱いやすい種類といえるでしょう。
仮想通貨担保型(DAIなど)
仮想通貨担保型は、イーサリアムなどの暗号資産を担保に発行されるステーブルコインです。
代表例は「DAI」で、分散型組織MakerDAOによって運営されています。DAIの特徴は、中央管理者を持たず、スマートコントラクトで自律的に運用されている点です。
そのため、透明性と分散性が高いというメリットがあります。
ただし、担保となる暗号資産の価格が下落すると清算リスクが発生し、安定性が揺らぐ可能性があります。
したがって、仮想通貨担保型はDeFiでの活用に適している一方で、初心者よりも中級者以上の投資家向けといえるでしょう。
商品担保型(金連動XAUTなど)
商品担保型は、金や原油といった実物資産に価値を連動させたステーブルコインです。
代表的な例は「XAUT」で、1枚のコインが1トロイオンスの金に対応しています。
これにより、暗号資産でありながら金の安定性を取り込み、インフレ対策や資産分散に活用できます。暗号資産の利便性と実物資産の信頼性を兼ね備えているのが魅力です。
しかし一方で、商品相場の価格変動には影響を受けるため、常に安定しているわけではありません。
投資家にとっては、「実物資産の裏付け」を重視するときに選ぶべき種類といえるでしょう。
アルゴリズム型(UST崩壊の事例も解説)
アルゴリズム型は、担保資産を持たず、市場の需給を調整するプログラムによって価格を維持しようとする仕組みです。
理論的には魅力的ですが、実際には安定性を保つことが難しく、リスクが高い点が課題です。
代表例の「UST(TerraUSD)」は、関連トークンLUNAとの交換メカニズムで1ドル維持を目指しましたが、2022年に暴落し数十兆円規模の損失を招きました。
この事件はアルゴリズム型の危険性を市場全体に知らしめた大事件となりました。
つまり、アルゴリズム型は革新的ではあるものの、実用性や信頼性には大きな課題が残る種類といえるでしょう。
ステーブルコインが注目される理由
ステーブルコインが近年注目を集めているのは、価格の安定性・国際送金や電子決済での実用性・規制当局や金融機関の関心という3つの要素が大きな背景にあります。
暗号資産市場は変動が激しく、従来の仮想通貨では決済や資産保全に不安がありました。
その中でステーブルコインは、「安定した価値を持ちながら暗号資産の利便性を維持する」という点で存在感を高めています。
価格の安定性とボラティリティの低減
暗号資産市場は値動きが大きく、短期間で価格が数十%変動することも珍しくありません。
そのため、投資家や企業にとってはリスクの高い通貨となっていました。
ステーブルコインは、法定通貨や資産と連動(ペッグ)する仕組みによって価格を一定に保つため、極端な値動きを避けることができます。
例えば、USDCやUSDTは常に1ドル前後を維持しており、市場全体が下落しても安定した価値を提供します。この「価格安定性」こそが、資産保有や決済手段としてステーブルコインが選ばれる最大の理由です。
国際送金・電子決済への実用性
従来の国際送金は、手数料が高く、着金まで数日を要するのが一般的でした。
これに対してステーブルコインは、ブロックチェーンを利用することで低コストかつ即時性のある送金を可能にします。
特にUSDCやJPYCは、24時間365日利用できるデジタル決済手段としての利便性が高く評価されています。
また、越境ECやフリーランスへの海外報酬支払いなど、グローバルに広がる取引のインフラとしても活用されています。
つまり、ステーブルコインは単なる投資商品ではなく、日常の実用的な決済ツールとして定着しつつあるのです。
規制当局や金融機関が注目する背景
ステーブルコインが注目されるもう一つの理由は、規制当局や金融機関が積極的に関与を始めている点です。
日本では金融庁がJPYCを承認し、資金決済法に基づく電子決済手段として法的に位置付けました。
米国でも、ステーブルコイン発行体に対して準備金や透明性を義務付ける規制法案が成立し、EUでもMiCA規制が導入されています。
さらに、大手銀行や決済事業者が参入を進めており、「安心して利用できるデジタル通貨インフラ」としての期待が高まっています。
規制と金融機関の後押しにより、ステーブルコインは今後さらに社会実装が進むと見込まれます。
【一覧と比較】代表的なステーブルコイン銘柄と選び方のポイント
ステーブルコインは数多く存在しますが、銘柄ごとに特徴や利用シーンが異なります。特に利用者が多いのは米ドル連動型のUSDC・USDT、国内で使いやすいJPYC、そして分散型のDAIです。
初心者が迷いやすいポイントですが、表を使って整理すると違いがわかりやすくなります。以下では代表的な4種類を比較してみましょう。
代表的なステーブルコインの比較表
| 銘柄 | 連動対象 | 発行体 | 主なメリット | 主なデメリット | 向いている用途 |
| USDT | 米ドル | Tether社 | 世界最大の流通量、対応取引所が多い | 準備金の透明性に不安 | 流動性重視、海外取引 |
| USDC | 米ドル | Circle社(監査済) | 高い透明性と信頼性、規制準拠 | 流通量はUSDTより少ない | 安全性重視、国際送金 |
| JPYC | 日本円 | JPYC株式会社 | 金融庁承認済み、円建て利用可能 | 世界的な流通量は少ない | 国内決済、円建て資産保有 |
| DAI | 仮想通貨 | MakerDAO(分散型) | 中央管理者不在で透明性が高い | 担保資産の価格下落で清算リスク | DeFi運用、中級者以上 |
銘柄選びのポイント
- 国内利用を優先するなら JPYC
- 流通量と利便性を重視するなら USDT
- 信頼性・監査体制を重視するなら USDC
- DeFi活用を目的とするなら DAI
【米ドル連動】USDC・USDT:信頼性と流通量を比較
米ドルに連動するステーブルコインの代表がUSDCとUSDTです。
どちらも1ドル≒1コインの価値を維持し、世界中で幅広く利用されています。
USDTは世界最大の流通量を誇り、ほぼすべての暗号資産取引所で利用可能です。その利便性から取引や送金で最も多く使われています。
一方で、準備金の透明性に疑問が持たれる場面もあり、規制当局からの監視が強まっています。
対してUSDCはCircle社が発行し、定期的に監査報告を公開するなど透明性を徹底しているのが強みです。
流動性ならUSDT、信頼性ならUSDCと、利用目的に応じて使い分けるのが賢明です。
【日本円連動】JPYC:国内発プロジェクトの現状と将来性
JPYCは、1JPYC=1円の価値を持つ日本円連動型ステーブルコインです。
2025年に金融庁の承認を受け、資金決済法に基づく電子決済手段として正式に位置づけられました。
これにより、国内のオンラインショップや加盟店で利用できるなど、実用性が一気に拡大しています。
また、円建てで直接利用できる点は、日本のユーザーにとって非常に大きなメリットです。
今後は銀行や大手決済事業者との連携が進めば、キャッシュレス決済や越境ECでの導入が加速すると期待されています。JPYCは、国内利用を中心に考えるユーザーに最も適したステーブルコインといえるでしょう。
【分散型】DAI:DeFiで活用したい中級者向け
DAIは、イーサリアムなどの暗号資産を担保に発行される分散型ステーブルコインです。
中央管理者を持たず、スマートコントラクトによって自律的に運営される点が特徴です。このため、透明性と分散性が高いという強みがあります。
一方で、担保となる暗号資産の価格が下落すると清算リスクが発生するため、安定性が揺らぐ可能性があります。
そのため、初心者よりもDeFi(分散型金融)を理解している中級者以上の投資家向けです。
レンディングやステーキングなど、積極的な資産運用を行いたい層に適した選択肢といえるでしょう。
初心者はどれを選ぶべき?目的別おすすめ銘柄
ステーブルコインは種類ごとに特徴が異なるため、利用目的に合わせて選ぶのがポイントです。
- 国内での決済や円建て利用を優先 → JPYC
- 海外取引や流動性重視 → USDT
- 透明性・信頼性を重視して資産を保有 → USDC
- DeFiでの活用を目的とする中級者以上 → DAI
ステーブルコインのメリットと活用方法
ステーブルコインは、価格の安定性・国際送金での利便性・資産運用での活用など、多くのメリットを持つ暗号資産です。
特に投資家にとっては、相場急落時の資産避難先として機能する一方で、企業にとっては低コストかつ迅速な決済手段として価値を発揮します。
また、DeFiやスマートコントラクトを通じて新しいユースケースが次々と生まれており、投資・決済・テクノロジーの交点にある存在として注目されています。
価格の安定による資産保有・リスク分散
ステーブルコインの最大のメリットは、価格の安定性です。
ビットコインのように大きく値動きする資産と異なり、ステーブルコインは法定通貨や資産に連動しているため、資産保有時のボラティリティを大幅に低減できます。
例えば、投資家は相場が急落した際に保有資産をUSDCやUSDTに切り替えることで、価値を維持しながら次の投資機会を待つことが可能です。
つまり、ステーブルコインはリスク分散の手段として非常に有効な資産といえます。
決済手段・国際送金の効率化
従来の国際送金は、手数料が高く、着金まで数日かかるのが一般的でした。
これに対してステーブルコインは、ブロックチェーン上で即時かつ低コストで送金できるという強みを持っています。
例えば、USDCやJPYCを利用すれば、24時間365日、数分以内での送金や決済が可能です。
特に越境ECやフリーランス報酬の支払いなど、国境を越えた取引の新しいインフラとして活用が広がっています。
これにより、ステーブルコインは単なる投資商品を超え、グローバルなデジタル決済手段として位置付けられています。
DeFi(レンディング・ステーキング・アービトラージ)での活用
ステーブルコインは、DeFi(分散型金融)分野での主要な基盤通貨として利用されています。
- レンディング:ステーブルコインを貸し出すことで利息収入を得られる
- ステーキング:一定期間預けることで報酬を得られる
- アービトラージ:複数市場の価格差を利用して利益を得る
特にDAIやUSDCは、DeFiプラットフォームの中心的な流動性資産として使われています。
価格が安定しているため、投資家は高い利回りを得ながらリスクをコントロールできる点が魅力です。
ブロックチェーンとスマートコントラクトによるユースケース拡大
ステーブルコインは、スマートコントラクトを通じて多様なユースケースに展開されています。
たとえば、自動化された決済システム・サプライチェーン管理・NFT取引の決済手段など、ブロックチェーンアプリケーションの土台として機能しています。
これにより、企業は従来の金融インフラでは実現できなかったスピードと透明性の高い取引を可能にしています。
将来的には、保険・不動産・ゲーム分野など、さらに幅広い産業で活用が進むと考えられます。
ステーブルコインのリスク・注意点
ステーブルコインは安定性を重視した暗号資産ですが、必ずしもリスクがゼロではありません。
発行体の信頼性や透明性に課題がある場合や、市場の急変動による価格下落リスクが存在します。さらに、各国の規制強化や市場競争によって、一部銘柄が淘汰される可能性もあります。
これらのリスクを理解した上で利用することが、安全に資産を守るための第一歩です。
発行体の信頼性と透明性の問題
ステーブルコインの価値は、発行体がどれだけ信頼できるかに大きく依存しています。準備金の保有状況や運用体制が不透明な場合、ペッグを維持できなくなるリスクがあります。
例えば、USDTは世界最大の流通量を誇りますが、準備金の内訳については過去に疑問視され、規制当局から監視を受けてきました。
対してUSDCは定期的に監査を公開しており、透明性の面で評価されています。投資家にとって重要なのは、「どの発行体が信頼できるか」を常に確認することです。
価格下落や暴落リスク(UST崩壊の事例)
ステーブルコインは理論上「安定資産」ですが、価格下落や暴落のリスクが存在します。
代表的な例が2022年のUST(TerraUSD)崩壊です。USTはLUNAトークンとの交換メカニズムによって1ドルの価値を維持しようとしましたが、大量売却によってシステムが破綻し、1ドルを大きく割り込みました。
この結果、数十兆円規模の損失が発生し、多くの投資家が資産を失いました。
この事例は、アルゴリズム型コインの脆弱性を示す象徴的な事件であり、安定性をうたうステーブルコインでも油断はできないことを証明しました。
各国規制(金融庁の資金決済法・米国の規制強化)
ステーブルコインはその影響力の大きさから、各国の規制対象として注目されています。
日本では金融庁が資金決済法に基づき、JPYCを承認しつつ、外国発行ステーブルコインの利用上限を100万円と制限しました。
米国では、ステーブルコイン発行体に対して準備金の保有や透明性を義務付ける法案が成立。EUでもMiCA規制が導入され、世界的に厳格化が進んでいます。
規制は利用者保護の観点から重要ですが、同時に一部銘柄の取引制限や利用ハードルが高まるリスクもあるため注意が必要です。
一部銘柄の淘汰リスク
ステーブルコイン市場は拡大していますが、すべての銘柄が生き残れるわけではありません。
裏付け資産の不備や運営体制の問題があるコインは、規制や市場競争によって淘汰される可能性があります。
過去にはBUSD(Binance USD)が規制強化の影響で新規発行を停止する事態となりました。
今後も信頼性に欠ける銘柄や、実用性の低いコインは市場から消えていくと考えられます。利用者は、「世界的に流通量が多く、透明性が高い銘柄を選ぶ」ことがリスク回避につながるでしょう。
日本におけるステーブルコインの現状と将来性
日本では2025年に入り、ステーブルコインの実用化が現実のものとなりつつあります。
金融庁の承認を受けたJPYCをはじめ、複数の国内プロジェクトが進展しており、円建てで利用できる利便性が注目されています。
さらに、規制の枠組みが整備されることで、投資家にとっては安全性が高まり、企業にとっては新しい決済インフラの導入チャンスとなっています。
ここからは、日本における最新動向と将来性を解説します。
JPYCや国内プロジェクトの進展
日本円に連動するJPYCは金融庁の承認を受けた初の円建てステーブルコインとして大きな注目を集めています。
現時点では本格的な普及には至っていないものの、オンライン決済や一部サービスでの実証実験・試験的導入が始まっており、円建てで直接利用できる可能性が示されています。
さらに、GMOやSBIといった大手企業も独自の円建てコインを検討しており、複数の国内プロジェクトが並行して進展しています。
これにより、円建てステーブルコイン市場は今後さらに拡大する見通しです。
金融庁の規制・法整備の方向性
金融庁はステーブルコインを「資金決済法に基づく電子決済手段」として位置づけ、利用者保護と市場の健全性を両立させる方針を打ち出しています。
具体的には、発行体に対して準備金の保有や透明性の確保を義務付け、不正利用や資金流出のリスクを最小限に抑える仕組みを構築しました。
また、外国発行のステーブルコインには利用上限(100万円)を設けるなど、段階的に規制を整えています。
これにより、安全性を担保しつつ市場拡大を促進する枠組みが整いつつあります。
電子決済手段・銀行連携による普及可能性
ステーブルコインは今後、電子決済手段としての利用拡大が期待されています。
特に、銀行や決済事業者との連携が進めば、コンビニやECサイト、公共料金の支払いなど、日常生活に直結する場面での利用が広がります。
さらに、ブロックチェーン上で即時決済が可能になることで、既存のキャッシュレス決済よりも低コストかつ迅速な取引が実現できます。
銀行が発行や流通に関与すれば、ユーザーにとっての信頼性も高まり、普及スピードはさらに加速するでしょう。
投資家・企業にとっての市場成長性
投資家にとって、日本市場でのステーブルコイン拡大はリスク分散や資産保有の選択肢拡大につながります。
企業にとっても、国際送金や越境ECの効率化、コスト削減という実務的メリットがあります。
さらに、国内外の規制が整うことで、大手金融機関や上場企業も参入しやすい環境が整備されつつあります。
結果として、ステーブルコインは投資対象としてだけでなく、企業活動の基盤インフラへと進化していく可能性が高いのです。
ステーブルコインが買える日本の取引所はどこ?
日本では、金融庁の規制整備が進んだことで、国内の登録済み暗号資産取引所でもステーブルコインの売買が可能になってきました。
以前は海外取引所を使う必要がありましたが、現在はCoincheck・bitbank・SBI VCトレードなどで取り扱いが開始されています。
これにより、初心者でも国内の安全な環境でステーブルコインを購入・利用できる時代が到来しました。
Coincheck(DAIなど)
Coincheckは、日本で最も利用者の多い暗号資産取引所のひとつで、DAIなど一部のステーブルコインを扱える数少ない国内プラットフォームです。
スマホアプリが使いやすく、初心者でも比較的スムーズに取引を始められるのが強みです。
現状、JPYCを直接購入することはできませんが、今後の法整備や取引所の対応拡大によって、国内での取扱いが広がる可能性があります。
ステーブルコインの取引を国内で安心して始めたい方にとって、Coincheckは有力な選択肢といえるでしょう。
bitbank(DAIなど)
bitbankは、セキュリティ水準が高いことで知られる取引所で、DAIの取り扱いを開始しています。
ビットコインやイーサリアムなど主要通貨と合わせて売買できるため、暗号資産投資と並行してステーブルコインを保有したい投資家に適しています。
加えて、手数料が比較的低いため、長期保有や定期的な取引を考えるユーザーにメリットが大きいのも特徴です。
SBI VCトレード(USDCなど)
SBI VCトレードは、大手金融グループのSBIが運営する取引所で、米ドル連動型のUSDCを取り扱う国内唯一のプラットフォームです。
大手金融機関が関与していることから、高い信頼性と安心感が得られるのが強みです。
特に、国際送金やドル建て取引を意識する投資家にとっては有力な選択肢となります。また、既存のSBI銀行口座との連携もしやすく、スムーズな入出金環境が整備されています。
その他の取扱いと今後の動き
今後、日本国内の取引所では、さらに多様なステーブルコインの取り扱いが拡大する可能性があります。
金融庁の規制整備が進んだことで、海外で主流のUSDTや他の法定通貨連動型コインも導入される見通しがあります。
特に、円建てだけでなくドルやユーロ建てコインが取引可能になれば、越境取引や国際決済における利便性は飛躍的に向上するでしょう。
今後は大手取引所を中心に取り扱い銘柄が増え、国内投資家が海外に依存せずに安心して取引できる環境が整うと考えられます。
【初心者向け】ステーブルコインの始め方・日本での買い方
ステーブルコインを購入するには、国内の暗号資産取引所を利用するのが最も安全でシンプルです。
基本の流れは以下の3ステップです。
- 取引所で口座を開設する
- 日本円を入金して暗号資産を購入する
- 目的のステーブルコインと交換する
銘柄によっては直接円建てで買えるものと、一度ビットコインやイーサリアムを経由して購入する必要があるものがあります。それぞれの違いを理解して、自分の目的に合った方法を選ぶことが大切です。
ステップ1:国内の暗号資産取引所で無料口座開設
まずは、金融庁に登録済みの取引所で口座を開設します。
代表的なのはCoincheck・bitbank・SBI VCトレードなどです。
口座開設には、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)の提出が必要ですが、数日程度で承認され、すぐに取引を始められるのが一般的です。
初心者は、アプリが使いやすく取扱銘柄も多いCoincheckから始めるのがおすすめです。
ステップ2:日本円を入金し、目的の暗号資産を購入(※)
口座開設が完了したら、銀行振込やコンビニ入金で日本円を取引所に入金します。その後、目的の暗号資産を購入します。
ここで注意したいのが、直接円建てで購入できる銘柄と、BTCやETHを経由して購入する銘柄がある点です。
- 直接円建てで買える銘柄:現状ではDAIなど一部に限られる
- 経由が必要な銘柄:USDT、USDC、そしてJPYCも含まれ、まずBTCやETHを購入してから交換する
この違いを理解しておくことで、余計な手数料を避け、スムーズにステーブルコインを入手できるようになります。
ステップ3:購入した暗号資産でステーブルコインと交換
取引所で直接購入できない銘柄(例:USDT・USDC)は、まずBTCやETHを購入し、その後にステーブルコインへ交換します。
国内で対応していない場合は、海外取引所やDeFi(分散型取引所)を利用する方法もあります。
ただし、海外取引所は規制リスクやセキュリティリスクがあるため、初心者はまず国内で買えるJPYCやDAIから始めるのが安心です。
購入したコインは、取引所の口座に置きっぱなしにせず、ウォレットに移して管理するのが安全です。
ステーブルコインに関するよくある質問
ステーブルコインは新しい資産クラスであるため、初心者から上級者まで多くの疑問や不安を持っています。ここでは代表的な質問を取り上げ、わかりやすく解説します。
ステーブルコインで利益を得る方法は?(ステーキング・DeFi)
ステーブルコイン自体は価格が安定しているため、値上がり益を狙う投資商品ではありません。しかし、利息や報酬を得る仕組みを活用すれば利益を狙うことが可能です。
- ステーキング:一定期間ステーブルコインを預けることで報酬を得られる
- レンディング:貸し出しによって利息を得る
- DeFi運用:分散型金融で利回りを獲得する
特にUSDCやDAIはDeFiでの利用が広く、利息収入や利回り獲得の手段として投資家に利用されています。
円建てステーブルコインは安全か?
円建てステーブルコイン(例:JPYC)は、金融庁の承認を受けて電子決済手段として位置づけられているため、法的な裏付けがあります。
ただし、発行体の信頼性や準備金の管理方法が安全性を左右します。
JPYCは規制に準拠して運営されていますが、まだ市場規模は小さく、流動性の面では米ドル連動型に劣る点もあります。
つまり、安全性は一定水準で確保されているものの、利用目的に応じて選ぶことが重要です。
将来すべての暗号資産がステーブルコインになるのか?
結論としては、すべての暗号資産がステーブルコインに置き換わる可能性は低いです。
ビットコインやイーサリアムは依然として「投機性」や「分散性」を重視する投資対象であり、その価値はステーブルコインとは異なる性質を持ちます。
一方で、決済や送金といった日常利用の多くはステーブルコインが担うと考えられます。
つまり今後は、価格変動が大きい資産と安定的な資産が共存するハイブリッドな市場になるのが現実的なシナリオです。
まとめ|ステーブルコインは投資と決済の新しいインフラ
ステーブルコインは、価格の安定性と暗号資産の利便性を両立させた新しい金融インフラです。
投資家にとってはリスク回避や資産保全の手段となり、企業にとっては国際送金や電子決済を効率化するツールとして期待が高まっています。
本記事で解説したポイントを改めて整理すると以下のとおりです。
- 注目される理由
- 価格の安定性によりリスク分散が可能
- 国際送金や電子決済を低コスト・即時で実現
- 規制当局や金融機関の後押しによる利用拡大
- 代表的な銘柄
- USDT:世界最大の流通量を誇る
- USDC:監査済みで透明性が高い
- JPYC:金融庁承認の円建てコイン、国内利用に強み
- DAI:分散型でDeFi運用に適した中級者向け
- 留意すべきリスク
- 発行体の信頼性や準備金の透明性
- 規制強化や市場淘汰による取引制限の可能性
- アルゴリズム型に代表される暴落リスク
これから始める方は、まずは国内取引所で扱える銘柄(例:DAIなど)からスタートするのが安心です。
今後の法整備や取扱い拡大により、国内でも選べる銘柄が増えていく可能性が高いため、最新の動向をチェックしながら利用範囲を広げていくと良いでしょう。
ステーブルコインは今後、投資と決済をつなぐ基盤的存在として、日常生活やビジネスに広がっていくことが予想されます。
今のうちから基礎を理解し、実際に少額から試してみることで、未来の金融インフラを先取りできるはずです。

DMM FXは、最短1時間で取引ができるFX口座です。新規口座解説の申し込みは約5分で完了します。
また、取引量に応じて最大30万円のキャッシュバックを受けられます。
この機会に申し込んでみてはいかがでしょうか?